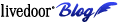2009年01月23日
終身雇用終焉のはじまり(副業禁止規定の解除について)
地味だが、日本における労働環境の転換点になりそうなニュースが流れていた。
岡山県倉敷市の三菱自動車工業水島製作所が、大幅な生産調整に伴う給料の減少を補うため、正社員にアルバイトを認める異例の措置を取っていることがわかりました。三菱自工 正社員のバイト許可
同社は月に8日しか操業しないという。(出勤しない)操業しない日には85%の賃金が支払われるとのこと。
休日と労働が完全に逆転してしまっている。稼動がこれ以上下がるようなら、希望退職ではなく、整理解雇もやらざる得ないだろう。
一定額は保障されるとは言え、年収の激減は避けられない。そこで副業禁止規定の解除、つまりアルバイトを認めることとなった。
労働法上は「禁止する」根拠はないと言われているけれども、就業規則を見ると、副業禁止規定がある会社は多い。それは情報漏洩であったり、面子であったりさまざまは理由はあるが、要は会社が個人の人生を支えるということも意味する。
家業である農業や不動産賃貸業について目こぼしされていたり、把握できない取っ払いの水商売、アルバイトをしたりしている人もいるが、少数派。
住民税を自分で払いに行ってごまかしながら副業している人は少ない。
副業を禁止しても「生活していける給料を与えている」との暗黙の前提がある。
すなわち、企業が労働者の労働力(結婚や子供を持つライフプラン)を丸抱えして、(出向など有期を含め)終身雇用を維持する前提することを意味していた。
この解除は本来自由であるはずの労働者の時間的自由を解放するとともに、「将来は保障できない」、つまり終身雇用の終焉を予感させる。
同一労働、同一賃金を安易に叫ぶ人がいるけれども、それも年功序列、年齢とともに給料が上がるシステムの崩壊をも示唆することを意識していないように思う。
公務員を志向する人は無意識に「システム維持を望んでいる」ように思える。
若い間は年齢で差があることに不満を覚える。一方で、自分が年長になったときに給料が上がることを望んでいる。
私は以前から「副業禁止規定の解除」には賛成派だ。
理由は、業界が長くなるほど、「社内の常識は世間の非常識」として窓が小さくなっていく、他の業界を内から見ることは、企業にとっても個人にとってもよい影響をもたらすと考えているからである。
また、成果主義的給与体系への移行によって、年収が上がらない、または下がる従業員の生活破綻、モラールの低下を懸念するからだ。
ただし、それはやむをえない流れとしての打開策であり、できれば、ある程度のピラミッドを維持していくような制度も必要だなというのが感想だ。
アルバイトを認める、兼業を認めることによって、転職は比較的容易になる。
社内外で培ったスキルを他で使う機会が発生する。つまり、労働に対して流動性が生まれる。アルバイトの報酬が正社員のそれよりも高く、将来性が見出せるならば、辞めることをいとわなくなる。
終身雇用、副業禁止の中ではこのようなことは起きなかった。転職に対するお試し期間がなかったから、博打性が高く尻込みする人も多いのは当然だった。
 サバイバル副業術 (ソフトバンク新書)
サバイバル副業術 (ソフトバンク新書)
著者:荻野 進介
販売元:ソフトバンククリエイティブ
発売日:2009-07-16
おすすめ度:
クチコミを見る
しかし、アルバイトとはいえ、労働で社外評価が得らることによって、社内でしか通用しない人は低い価格が、社外で高く評価される人は妥当な価格がつく。
流動的になるということは、いっとこにとどまる終身雇用の終焉を意味する。
 副業で生き抜く!
副業で生き抜く!
著者:副業推進委員会
販売元:ブックマン社
発売日:2009-10-22
おすすめ度:
クチコミを見る
今日現在では操業停止というわかりやすいブルーカラーにのみ認められたけれども、この議論は活発になり、同一労働・同一賃金とともにホワイトカラーに波及するのは自然の流れだろう。
日本の労働における「三種の○○」労使協調、年功序列、終身雇用の崩れる音が聞こえる。
たぶんそのひとつが副業禁止規定の解除であり、後で「転換点だったね」といわれるに違いない。
ますます自己防衛の体制を整えなくてはならない。今まで「会社でできる人」だけで生きていくのはたいへんになるだろう。

 日本型「成果主義」の可能性
日本型「成果主義」の可能性
著者:城 繁幸
販売元:東洋経済新報社
発売日:2005-04-15
おすすめ度:
クチコミを見る
 ワーキングプア いくら働いても報われない時代が来る (宝島社新書)
ワーキングプア いくら働いても報われない時代が来る (宝島社新書)
著者:門倉 貴史
販売元:宝島社
発売日:2006-11-09
おすすめ度:
クチコミを見る
休日と労働が完全に逆転してしまっている。稼動がこれ以上下がるようなら、希望退職ではなく、整理解雇もやらざる得ないだろう。
一定額は保障されるとは言え、年収の激減は避けられない。そこで副業禁止規定の解除、つまりアルバイトを認めることとなった。
労働法上は「禁止する」根拠はないと言われているけれども、就業規則を見ると、副業禁止規定がある会社は多い。それは情報漏洩であったり、面子であったりさまざまは理由はあるが、要は会社が個人の人生を支えるということも意味する。
家業である農業や不動産賃貸業について目こぼしされていたり、把握できない取っ払いの水商売、アルバイトをしたりしている人もいるが、少数派。
住民税を自分で払いに行ってごまかしながら副業している人は少ない。
副業を禁止しても「生活していける給料を与えている」との暗黙の前提がある。
すなわち、企業が労働者の労働力(結婚や子供を持つライフプラン)を丸抱えして、(出向など有期を含め)終身雇用を維持する前提することを意味していた。
この解除は本来自由であるはずの労働者の時間的自由を解放するとともに、「将来は保障できない」、つまり終身雇用の終焉を予感させる。
同一労働、同一賃金を安易に叫ぶ人がいるけれども、それも年功序列、年齢とともに給料が上がるシステムの崩壊をも示唆することを意識していないように思う。
公務員を志向する人は無意識に「システム維持を望んでいる」ように思える。
若い間は年齢で差があることに不満を覚える。一方で、自分が年長になったときに給料が上がることを望んでいる。
私は以前から「副業禁止規定の解除」には賛成派だ。
理由は、業界が長くなるほど、「社内の常識は世間の非常識」として窓が小さくなっていく、他の業界を内から見ることは、企業にとっても個人にとってもよい影響をもたらすと考えているからである。
また、成果主義的給与体系への移行によって、年収が上がらない、または下がる従業員の生活破綻、モラールの低下を懸念するからだ。
ただし、それはやむをえない流れとしての打開策であり、できれば、ある程度のピラミッドを維持していくような制度も必要だなというのが感想だ。
アルバイトを認める、兼業を認めることによって、転職は比較的容易になる。
社内外で培ったスキルを他で使う機会が発生する。つまり、労働に対して流動性が生まれる。アルバイトの報酬が正社員のそれよりも高く、将来性が見出せるならば、辞めることをいとわなくなる。
終身雇用、副業禁止の中ではこのようなことは起きなかった。転職に対するお試し期間がなかったから、博打性が高く尻込みする人も多いのは当然だった。
 サバイバル副業術 (ソフトバンク新書)
サバイバル副業術 (ソフトバンク新書)著者:荻野 進介
販売元:ソフトバンククリエイティブ
発売日:2009-07-16
おすすめ度:
クチコミを見る
しかし、アルバイトとはいえ、労働で社外評価が得らることによって、社内でしか通用しない人は低い価格が、社外で高く評価される人は妥当な価格がつく。
流動的になるということは、いっとこにとどまる終身雇用の終焉を意味する。
 副業で生き抜く!
副業で生き抜く!著者:副業推進委員会
販売元:ブックマン社
発売日:2009-10-22
おすすめ度:
クチコミを見る
今日現在では操業停止というわかりやすいブルーカラーにのみ認められたけれども、この議論は活発になり、同一労働・同一賃金とともにホワイトカラーに波及するのは自然の流れだろう。
日本の労働における「三種の○○」労使協調、年功序列、終身雇用の崩れる音が聞こえる。
たぶんそのひとつが副業禁止規定の解除であり、後で「転換点だったね」といわれるに違いない。
ますます自己防衛の体制を整えなくてはならない。今まで「会社でできる人」だけで生きていくのはたいへんになるだろう。
 日本型「成果主義」の可能性
日本型「成果主義」の可能性著者:城 繁幸
販売元:東洋経済新報社
発売日:2005-04-15
おすすめ度:
クチコミを見る
 ワーキングプア いくら働いても報われない時代が来る (宝島社新書)
ワーキングプア いくら働いても報われない時代が来る (宝島社新書)著者:門倉 貴史
販売元:宝島社
発売日:2006-11-09
おすすめ度:
クチコミを見る
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by Skipper Mo 2009年01月27日 21:54
副業禁止を明確化する会社は多かったのですが、今後は操業短縮がごく当たり前になれば、どこでも副業する人がみられるのかもしれません。
私はまだ求職中ですが、フリーターの人では、二つ掛け持ちして正社員よりいい給与を貰っている人もいます。
さて、社外に自分のスキルを試すことができる---というのはおもしろい見方だと思いますが、手に職を持っている工場の職人さんはできても、我々事務職・営業職にはすんなりいかないかもしれません。
ただ、転職目的ではなく、余暇を生かすという考えで見れば、博物館で案内役のボランティアという選択肢もあるわけで、私個人としては大変興味があります。おそらく何かと忙しい大都会よりも比較的時間の自由が利く郊外なら比較的すんなり導入しやすいと思います。
私はまだ求職中ですが、フリーターの人では、二つ掛け持ちして正社員よりいい給与を貰っている人もいます。
さて、社外に自分のスキルを試すことができる---というのはおもしろい見方だと思いますが、手に職を持っている工場の職人さんはできても、我々事務職・営業職にはすんなりいかないかもしれません。
ただ、転職目的ではなく、余暇を生かすという考えで見れば、博物館で案内役のボランティアという選択肢もあるわけで、私個人としては大変興味があります。おそらく何かと忙しい大都会よりも比較的時間の自由が利く郊外なら比較的すんなり導入しやすいと思います。
2. Posted by マリンゾウ 2009年01月28日 18:57
>Skipper Moさん
どうも。
「我々事務職・営業職にはすんなりいかないかもしれません。」
私はこの部分は職務として確立され、流動性を持つといいと思っています。
現在は日本では就職ではなく、就社になってしまい、その会社でしか必要としない知識・スキル・世渡りみたいなものが重視されているように思えてならないのです。
雇用の流動性は先の話とは思いますが、私は世間一般で通用するスキルを身に着けたいと思っていますし、自分より若い人にはそういう視点で話をします。
その方が若い人は受け入れやすく、結果的に流出は少ないように思います。
どうも。
「我々事務職・営業職にはすんなりいかないかもしれません。」
私はこの部分は職務として確立され、流動性を持つといいと思っています。
現在は日本では就職ではなく、就社になってしまい、その会社でしか必要としない知識・スキル・世渡りみたいなものが重視されているように思えてならないのです。
雇用の流動性は先の話とは思いますが、私は世間一般で通用するスキルを身に着けたいと思っていますし、自分より若い人にはそういう視点で話をします。
その方が若い人は受け入れやすく、結果的に流出は少ないように思います。
3. Posted by マリンゾウ 2009年01月28日 19:03
博物館で案内役のボランティアという選択肢もあるわけで、
同意です。退職してからの人生も長いですし、大学を大挙して闊歩する高齢者とか、(年齢に関わらず)社会にコミットする機会が増えるといいですね。
教育を受けるのも贅沢の一つですし、大学教授も年齢が上の人の前では緊張する。熱心に授業を聴く。
高齢者の授業料半額免除とか私立大学の生き残る道かもと思ったりもしました。
同意です。退職してからの人生も長いですし、大学を大挙して闊歩する高齢者とか、(年齢に関わらず)社会にコミットする機会が増えるといいですね。
教育を受けるのも贅沢の一つですし、大学教授も年齢が上の人の前では緊張する。熱心に授業を聴く。
高齢者の授業料半額免除とか私立大学の生き残る道かもと思ったりもしました。
4. Posted by 中山澄子 2009年02月04日 10:15
私もサラリーマンの副業大賛成です。 本業とは異なった世界に自分を置くことでリフレッシュできます。 別に旅行や飲み会だけが、リフレッシュでは、ありません。 また、定年退職後やリストラ対策として、在職中に、色々な経験やキャリアをつんでおくのは自衛措置だと思います。 今の勤務先がだめになったら即破滅する人間にならないような、日頃の努力は大切だと思います。
5. Posted by マリンゾウ 2009年02月05日 18:57
>中山澄子さん
いざルール作りとなると難しいのもまた事実なのです。
ただ、製造業は今後増えるでしょうね。
いざルール作りとなると難しいのもまた事実なのです。
ただ、製造業は今後増えるでしょうね。